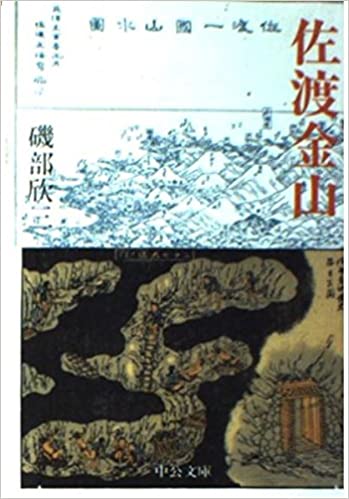
佐渡金山
磯部欣三 中央公論社 1992年 762円
著者は佐渡金山のあった相川の生まれで、佐渡博物館の館長をしていた人です。
書かれたのはだいぶ昔です。
内容は、
廃墟の文化史
地底の水替
大工と穿子
心中と盆踊り
金銀山の遊女
流人巡礼
技術の社会史
となっており、400p弱あります。誰も知らないような事柄がめちゃくちゃ詳しく書かれています。凄い調査と記録ですな。佐渡金山はこんなだったんですね。
うち、「金銀山の遊女」は56pあります。好きな人には面白いと思います。
ジャンル的には研究書になると思いますが、どことなく小説風に書かれている部分もあって、読みやすいです。
一番印象に残っているのは…。
坑道で湧き水を汲みだす作業員(水替)が、今でいう囚人労働であるにもかかわらず、あまりの重労働に一日に一升二合もの米を食わせてもらっていたというのと、穴を掘る作業員(穿子)が休憩時間も坑道から出ずに暗闇にずっと居たままで、元気なものでも数年で必ず死ぬ、というもの。何度読んでも信じられん。そら賃金貰ったら100%女買いに行くよな。
わたし、だいぶ昔に佐渡金山行ったことあるのですが、観光コースになっている坑道の中の動く人形が「馴染みの女に会いてえなア」って呟くんですよ。いまでも同じなのかな。